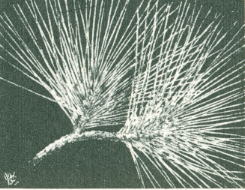| 車 前 草 時 (1p目/9pの内)  挿画 児玉悦夫 |
明治三十七年は旅順を主戦場とする日露の戦火のうちに年の瀬を迎えた。 十月二十六日、乃木希典大将の第三軍が第二回旅順総攻撃の火ぶたを切ったが、さすがに露軍頼みの堅城。四日間で我が軍の将兵の死傷三千八百三十人に達したが落ちない。 越えて十一月二十六日、一カ月の準備を重ねたうえで第三回総攻撃を開始した。死傷さらに一万六千九百三十五人を加える大激戦のすえ、十二月五日にようやく二〇三高地を占領するに至った。 砲撃によって二〇三高地はその形容を改め、敵味方の死屍るいるいとして山を築き、鮮血はほと走って川となった。 その形容があながち誇張と言い切れない惨状であった。 だが、銃後の国民に伝えられる情報の多くは捷報のみであった。ことに海軍の戦勝ぶりは向かうところ敵なしの観さえあった。 暮れの町のにぎわいは、その気分を反映してむしろいつもの年より華やかでさえある。 牧水らが、ほとんど毎日のように顔をさらす神田神保町の本屋街に並ぶ雑誌類は早くも新年号のきらびやかな表紙が餅を競っている。 そのうちの『文庫』には北原の長詩『全都覚醒の賦』が掲載されて注目を集めた。 北原白秋の出世作になったこの詩は、同年十一月初めから時には一睡もせずに想を練り、詩句をすいこうした苦心作である。 清致館に同宿して牧水は北原の砕身ぶりを知っている。この間、大学の授業にはほとんど顔を出さず、下宿とたまに図書館を往復するだけで、万葉、古事記など古典類と首っ引きの生活だった。 この詩は、早稲田の『早稲田学報』の懸賞文芸の第一位に当選、その後、編集者が請うて『文庫』に転載したものである。 『文庫』のほか、九月号に与謝野晶子の詩『君死に給ふこと勿れ』を掲載、大町桂月らとの間で論争を起こした『明星』、牧水の短歌を採用した『中央公論』など文芸雑誌の発行は多彩である。 町をゆく婦人たちの間で『二〇三高地』『花月巻』などの新しい髪形が流行したのもこの年の暮れである。『二〇三高地』はもちろん第三軍激戦の地名から名付けたものだ。当時の戦勝気分がうかがえる。 軍歌『天に代わりて不義を討つ…』も暮れの町に流れていた。 その圧巻は東郷平八郎海軍大将の凱旋であった。三十日、牧水も朝食もそこそこに下宿を飛び出して霞が関の道わきで連戦連勝の提督を迎えた。上村中将、島村参謀長ら勇将とともに道路の両側を埋める群衆に、東郷大将はにこやかに笑みを返していた。 |