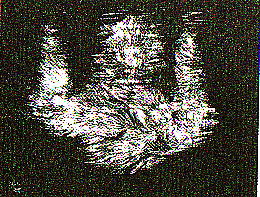| みなかみ紀行 (6p目/11pの内)  挿画 児玉悦夫 |
老案内者は、焼岳の煙が信州路なら雨。反対に飛騨になびけば晴れると言う。 『山の人たちの天気見は確かだからねえ』 牧水は感心してみせたうえで言葉を継いだ。 『ところで爺さん。どうしてもあの山に登るのはいやかね。そんなに危険なのかねえ』 『登れねえことはねェだが、永いこと登ってねえだから路がどうなっているだかサ』 『上高地の宿で詳しいことを聞けばいいじゃないか。大体のことは前々から知っているんだし、路もそう大した変わりはないよ』 牧水は、白骨から上高地、そこから飛騨に越して平場に回り、高山町に出て越中路を歩き、富山市から汽車で沼津に帰る考えだった。 上高地から平湯までの道を地図で見ると焼岳の麓を通っている。そこで焼山登りを宿の者に相談したのだが、十月半ばの焼岳登山は無理だとことわられた。 そして平湯までという約束でつけてくれたのが老案内者だった。 しかし、いま眼前に焼岳を見て牧水は登山の願望を押さえきれない。それから山路をたどりながら老案内者をくどいた。 『そうまで言うんなら今夜上高地温泉でよく聞いてみるだ。昔の路と変わりねえようだったらなあに心配はねえだ』 いかにも善人らしいあから顔の老案内者は牧水の執拗なまでの頼みに折れた。 牧水も『年寄りに無理を言って』と内心思わぬでもなかった。だが、それよりも念願がかなった喜びの方が大きかった。 自分でもおかしいほどそれからの足取りが軽くなった。 うら悲しき光のなかに山岨の道の辺の紅葉散りてゐるなり しばらく行くと上高地と平湯に道が分かれている。明日は焼岳から降りて飛騨に越える平湯への道を歩くことになる。そう思いつつ上高地への道を急いだ。 しばらくすると、これまで続いた紅葉の森林とは全く異なる地帯に行きあたった。そこには真白に枯れた巨木が林立していた。 大正四年六月六日朝、焼岳が突然大爆発を起こした。噴火口から流出した多量の泥流が梓川の本流をせき止め、霞沢岳と焼岳との間に面積約四十万平方㍍の大正池を作った。六年前のことだ。 この世の様とは思えぬ巨木の墓場はその時に熱灰をかぶったものだ。牧水らは背筋が寒くなる思いで逃げるようにこの地帯を抜けた。 その先には荒々しく波立つ溶岩の川原が開け、さらにその奥に大正池が満々と梓川の清流をたたえていた。 真青い湖面には先刻と同じ白い巨木が梢だけを見せていた。 |