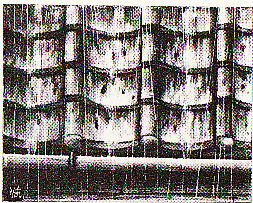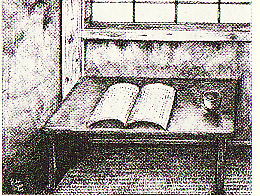| 早稲田時代 (3p目/16pの内) 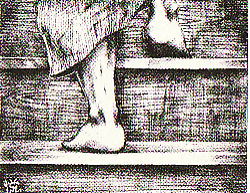 挿画 児玉悦夫 |
故郷の人とはだれだろう。不審に思いながらもあわてて階下に降りてみた。 玄関のたたきに背の高いがっちりしたタイプの若い男が突っ立っている。年齢は牧水とほぼ同じころだろうかー。 『若山ですが−。君は−』 『ぼくも東郷村出身です。海野実門と言います。小野葉桜君をたずねたんだけど、あいにく不在で−。弱って女中さんに相談したら同郷の若山さんがおいでだというんで、呼んでもらいました。遅くにすまんです』 『ああ、そうですか、東郷は、ぼくは坪谷だけど、海野君は』 『山陰の下の福瀬です。美々津にくだる途中の中ノ原から入った所ですよ』 そう聞いたら改まっていた言葉使いがいくらかぞんざいに変わってくる。 『まあ、とにかくあがろうや、立ち話もできんが』 二階の自室に案内した。起き抜けの布団を隅に押しやって二人あぐらをかいて向き合った。 坪谷と福瀬と言えば、東郷村の東と西の端同士だが、東京に来れば身内同然だ。遠慮はない。 話を聞くうちに互いの事情がわかってきた。 海野は、福瀬の小学校を出て宮崎中学校に入学した。牧水より四歳上だから延岡中の開校前だった。三十年春の入学で十回生になる。 二年前に宮崎中を卒業したが、この春まで日州独立新聞に勤めていた。五年生から学校の雑誌部長に選ばれ、校友会雑誌『望洋』を編集していた。印刷を頼んだことから新聞社の社長にも面識があった。 卒業のあいさつに行ったら社長が 『海野君、それであとはどうするね』 と聞いてくれた。 『実は東京に出たいんですが、家が貧乏なもんですから、二、三年こっちで働いてからにしようと思っています』 と、素直に打ち明けた。 『それじゃ社で働いちゃどうかね。社員も君の人物を知っているし、君だって気がねはいらんと思うがね』 渡りに舟だった。即座に頚をさげた。 翌日から出社したら『記者見習』の辞令をくれた。『望洋』の原稿を早くから書いていたからエンピツにはなれている。 先輩社口醇に重宝がられて二年余り記者生活を続けた。 『若山君、君の名前は歌の投稿で早くから知っていたんだよ。東郷にえらいもんができたもんじゃと驚いていたつよ』 それでますます二人の仲は打ちとけていった。縁はまことに異なものだ。 |