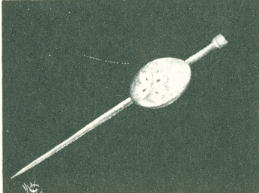| 結 婚 (6p目/8pの内)  挿画 児玉悦夫 |
塩尻駅から乗車した牧水は上諏訪駅で途中下車して旅館松川屋に泊った。とくりで四、五本はど酒を飲んだあと、喜志子あてに手紙を書いた。 『−早速御承知下さったことを深く深く感謝します。偶然のようで決して偶然でない。我等ふたりのために今日は本当に忘れ難い大切な日であるのです。私は何かは知らず、深い深い感謝の念が湧いて仕様がないのです。恐らくあなたにも斯くあるだろうと信じます。 今までは準備の日、過去の時、我らが本当に生まれるのは実に今日からだと存じます。あなたはそうは思いませんか。 あのかわいらしいお妹さんを怨むのでは決してない。けれども、そうと察していながら、濁りで来て下さらなかったあなたをうらめしく思います。 いつごろ東京においでになります。早くお目にかかりたいと存じます。 汽車の中から、湯槽の中から、ああだこうだと思っていましたが、いざとなると、何も筆にのりません。のせたくもありません。このまま黙って独りで思います。 つい目の前においでるようにもあり、こう手紙を書いているのに気がつけば、極めて遠き人のようにも思われます。鳴呼、四月二日、さようなら、あなたの夢の平安を祈ります。 四月二日、午後九時半、若山牧水』 この手紙にはもう一通同封してあった。それには小枝子との悲恋の始終とそれに伴って起きた煩悶。病気を患っていることなどを大胆率直に告白していた。 常識的には極力秘めておきたい事柄であった。だが牧水は、生涯の伴侶と思い定めた喜志子に赤裸々に打ち明けた。 それは、牧水の喜志子への愛が互いに一点のかげりさえ許さぬ真剣なものであることを示すものであった。 同時に、これまでの自堕落な生活態度から脱却して新しく生まれかわる彼の決意を表明するものでもあった。 分厚い手紙を手にした喜志子はすぐに封を切った。読み進むうちに涙があふれてきて文字がゆがんだ。 ことに過去の悲恋や乱れた生活ぶりをあからさまにした告白に感動した。知り合う前のことであっても無垢であって欲しい。愛する相手に対する願いは男女とも変わらない。 喜志子も同じである。だが、それを隠そうとしない牧水に、男らしさと愛の深さを思った。ふるえるほどの喜びを感じた。 彼女はその夜、ちゅうちょなく両親に牧水からの求婚を話した。そのことを予感していたようすの二人は普通の手順を望んだだけで結婚そのものに反対はしなかった。 |