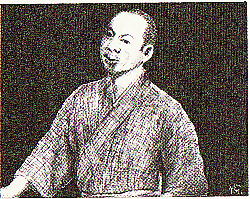| 武 蔵 野 (4p目/13pの内)  挿画 児玉悦夫 |
三十九年の元日を牛込区大久保余町の石原方で迎えた。故郷からの毎月きまりの送金が、暮れのうちに届いた。 都農からの送金は四円五十銭だった。十二月から神戸の長田からも毎月二円送ってもらえることになった。当面は学資や生活費に窮することはない。 何か、新しい年はよいことでもありそうな、弾むおもいさえしていた。 『恭賀新年 先月と言ひ本月と申しうれしき御こころがしのほど何とも御礼申しかぬるほどに候。よろしく御察し下され度候。おかげ様にて何とも言へぬうれしさを感じ申し候。この後とても万事よろしく御願ひ申上候』。 佐太郎あての年賀状にも率直な思いをしたためた。 父立蔵にも、義兄、叔父の温情を伝え、これからは一切迷うことなく勉強する旨書いてやった。母マキには、とりわけ長田の厚情に感謝していること、『母上よりもよろしくお伝え下され度』と追伸した。 正月三カ日は、久しぶりに海野ら延岡の滞京組が、たずねてきた。下宿にいてもしかたがないからそのたびに盛り場に出た。おたがいふところは潤沢ではないが、正月だ。安直に一杯くみかわすことになった。 酔余、ほてったほほを寒風になぶらせて武蔵野に出ることが多かった。土岐、前田夕暮をさそった日もあった。 延岡在住の関貞蔵にその辺の事情を知らせてやった。関は牧水の延岡中学校の後輩で『行渓』と号して詩歌をたしなんでいる。 牧水らの『曙』が、彼ら創刊当初からの同人が卒業するため、後継者として関らを勧誘して入会させたものだった。 新年早々に彼から年賀状が届いた。その返事を十日に出した。武蔵野を描いた三色刷りの絵はがきを細字で埋めた。 『私の姉なる武蔵野はこんな景色がいくつも集って出来て居るのです。今より折にふれてこんなのをお送り申しませう(中略)。お正月だといふので少し遊びすぎて明日からの学校が辛う御ざいます。寒いさむいで歌も出来ません。ただーつと思ふのを今日野虹に出しときました。国のお正月いかがてした。もう梅も咲きましたろう。 雲おほき冬の武蔵の榛原(はりはら)に薮うぐひすと春待ちにけり 『雲おほ今:』は新声二月号に掲載された。その一月号には、前年暮れに詠んだ七首を投稿した。 冬の丘は紅き花なしみどりなしただ天日の白う照りつつ 白菊やみやこにちかき里住みの男ばかりの家にみだれぬ |