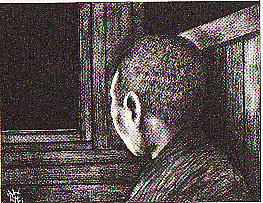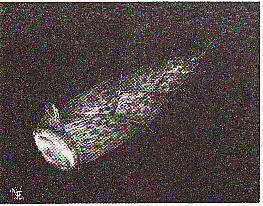| 巣 鴨 時 代 (5p目/5pの内)  挿画 児玉悦夫 |
大正七年の元旦の朝はあわただしかった。除夜の鐘が鳴り終わるとすぐに床を抜け出たのだから此の上はない。 真暗い庭に出て井戸から汲み上げた水で顔を洗い、四畳半の自分の部屋の火鉢の埋め火をかきたてて机に原稿用紙を広げた。だが、それを片付けて鉄瓶で湯を沸かして酒の徳利をつけた。 午前二時だ。喜志子を起こして朝餉の用意を言いつけてから、暮れの二十九日から出て来て泊まっている青森の創作社友加藤東籬を呼び起こして酒になった。 五時を柱時計が打つと急いで雑煮を祝って東籬を伴って家を出た。彼を三崎に案内することにして昨夜は早くから床についていたのだった。 船で行くつもりが休航だというので東京駅から横須賀行きの切符を買ったが、汽車に乗ってから気が変わった。鎌倉で途中下車して鶴ケ岡八幡、長谷の大仏、観音と回った。 ここから三崎に直行の予定だったが、観音堂から朝日にキラキラ輝やく海を見ているうちにまた気が変わった。伊豆の上肥温泉まで足を伸ばそう。 東籬に相談しても彼に異存があるはずもない。汽車て沼津まで行き狩野川口の旅館に泊まって翌朝の汽船で土肥に渡った。 伊豆西海岸の静かな温泉宿『明治館』に二泊して四日の夕刻、巣鴨の家に帰った。 この計画は、雪国から出て来た珍客に温暖な海浜の新年を味あわせてやろうと考えたことだった。一昨年の三月、初めてみちのくを旅したおりに初めて東籬に逢った。 もの言わぬ加藤東籬を見ばやとてはるばる急ぐ雪路なるかも 北国の人らしく口数が少なく重厚な人物であった。それでいて実に細い配慮かある。彼の家に数泊したが、我が家のように気がねなく過ごすことができた。 その返礼をしたかった。喜志子も快く応じて乏しい財布からそれなりの金を用意してくれていた。 巣鴨に帰れば例によって来客続き。平生でも客の顔を見れば酒を出さねばすまされぬ牧水である。正月中は幾つかの新年歌会をふくめてほとんど毎日が酒だった。 二月は七日から二十四日まで土肥温泉に滞在して散文集『海より山より』と歌集『寂しき樹木』の原稿を整理した。 四月二十二日には二女が生まれ、真木子と命名された。 五月から『短歌雑誌』に『おもいでの記』が連載され、九月号まで続いた。『庭梅』『牡丹桜』『祖父の事』など故郷坪谷の人と自然を追憶した小品集である。 |